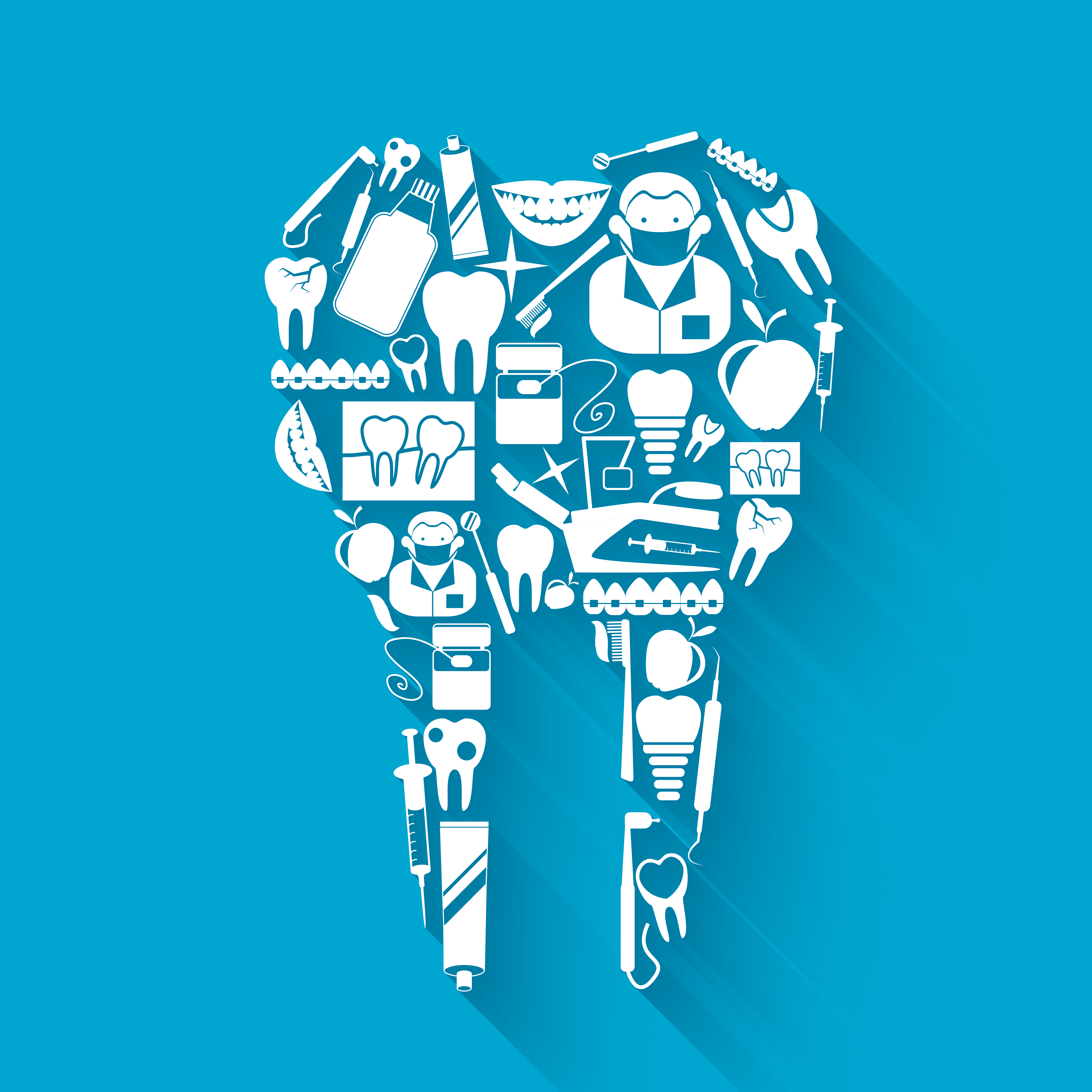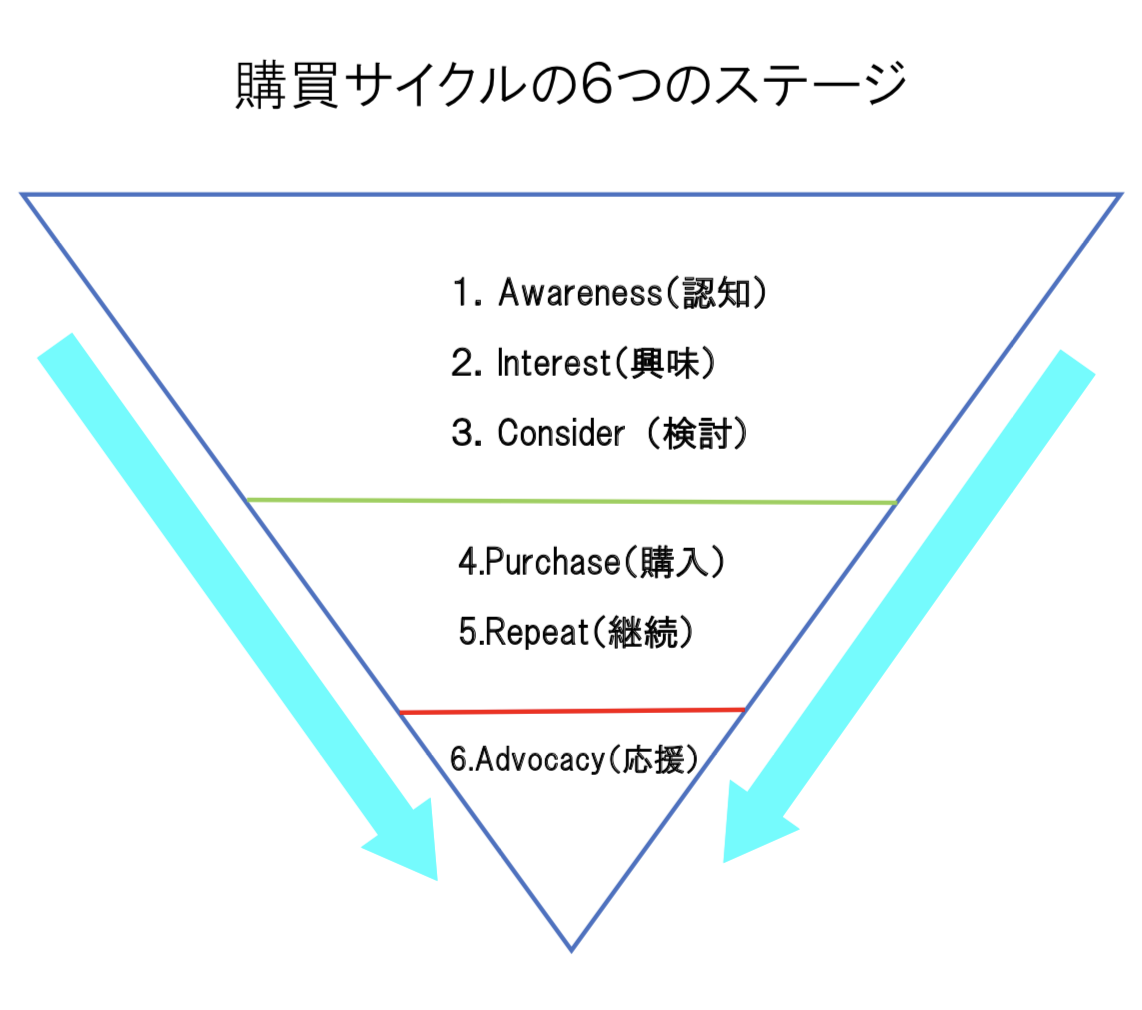この記事では、歯科技工士の実態から求人サイトなどで示されている歯科技工士の年収や労働環境が如何に信憑性の乏しい情報であるかを報告したい。
歯科技工士を目指す方々や、実態を正しく把握したい若手技工士のための「歯科技工士の本当の年収」の情報を提供するために。
求人サイトなどでは
「歯科技工士 年収」などのキーワードで検索すると、求人サイトなどで多く示されている歯科技工士の年収は、
求人サイト
- 平均年齢:40~50歳
- 勤続年数:10~20年
- 労働時間:170~180時間/月
- 超過労働:8~10時間
- 月額給与30~35万円
- 年間賞与40~45万円
- 平均年収:400~500万円
などと示している場合が多い。おそらく根拠となる資料は、
厚生労働省:賃金構造基本統計調査 から算出したものだと考えられる。しかし、鵜呑みにしてはならない。ハッキリ言って参考にならないデータなので、実態を示した正確なデータをこの記事では示したいと考える。
実態は以下の通り
まず、気になる「実態」を示した歯科技工士の年収と就労状況を示す。
実態
- 平均年齢:52~57歳
- 技工年数:10~20年
- 労働時間:60~90時間/週
- 月額給与17~33万円
- 平均年収:200~400万円
※労働時間は月ではなく週なのでお間違えないように。そのため、超過労働は労働時間に含む。
以上のデータの根拠は後で説明するとして、8時間労働で週休2日(一般常識を採用)でザックリ時給を算出すると時給170円ということになる。
「さすがに時給170円は無いやろ」と少しビビッてしまった。そこで、思い切って365日年中無休で働いた場合(一人コンビニのような感じ)の時給も示すと、大幅アップで755円となり、多くの自治体の最低賃金に少し及ばない程度となった。
※だが、本来は8時間労働、週休2日程度で算出するのが一般的だ。社会通念上、365日24時間労働で算出する時給や年収なんかは存在しない。
それでは、このデータの根拠を示していこう。
歯科技工士の特徴
はじめに求人サイトなどで示されている歯科技工士の年収がいかに実態を反映していないかを示す。そのためには歯科技工士の就労実態がどのような特徴があるのかを知る必要がある。
歯科技工士のほとんどは歯科診療所で雇用されているわけではない。歯科医師は患者さんの歯科技工物(入れ歯や、被せ物)を自分で作るわけではなく、患者さんの歯形を歯科技工所(ラボ)という製作現場に外注委託する。
簡単に言うと、歯医者さんから外注委託され、歯科技工物の製作を「歯医者さんの下請け」として作るのが歯科技工所ということになる。そこで入れ歯などを製作するのが国家資格を持った歯科技工士だ。
そして、この歯科技工所の特徴が、歯科技工所全体の80~90%が1~2人で歯科技工業を営む個人事業という事業形態だ。なので、ほとんどの歯科技工士は個人経営であるという大きな特徴がある。
歯医者さんのほとんどが個人経営で、イオン歯科やセブンアンドアイ歯科のような大型量販店型ではないのと同じイメージだ。
全ての歯科技工物は手作りで制作され、職人仕事であることは言うまでもなく、
- ほとんどの歯科技工士は歯科医院で雇用されているのではない。
- 歯医者の下請けとして歯科技工物の製作を請け負っている。
- そのほとんど(80~90%)が個人事業という経営形態である
という特徴がある。
実態を反映していない
そこで、歯科技工産業がブラック産業であるという根拠に入る前に、求人サイトなどで紹介されている歯科技工士の年収は「厚生労働省:賃金構造基本統計調査」を基に示してあるが、いかに実態を反映していないかを示す。
まず、この調査の特徴は
- 対象は10人以上の事業所
- 区分訳は、10~99人、100~999人、1000人以上
となっている。この時点で歯科技工士(所)の特徴を反映したものではない。
しかし、少数ではあるが大手技工所もある。そこに就職すると良いだけかと思われるかもしれないが、私たちが知る限り、大手歯科技工所が調査結果のような就労環境にあることはない。
では、なぜ実態と調査結果にこれだけの開きが生じるのだろうか?明確な理由は分からないが、私たちはこう考える。
この調査は厚生労働省によって行われている。そして歯科技工士を所管するのも厚生労働省だ。さらに技工所の従業員ではなく、報告するのは技工所の経営者だ。
そのことから、ブラック企業である技工所が、自らを所管する厚生労働省にそのまま「ブラック企業です」と報告するはずがないではないか?
歯科技工士の年収と労働実態
では、実態はブラック産業であるという根拠を示す。冒頭から繰り返している「実態」ということがカギとなる。歯科技工所の実態を示した調査データがある。
歯科技工士実態調査
はじめに紹介するのは、公益社団法人「日本歯科技工士会」が定期的に行っている歯科技工士実態調査というものがある。
実際のデータは、こちらの2015歯科技工士実態調査を参考にしていただきたい。ここから、自営者の労働状況と歯科技工士の年収を示すと以下のようになる。
2015歯科技工士実態調査
- 平均年齢:53.6歳
- 休日:週0.9日
- 週労働時間:平均は68.9時間
- 平均年収:255.3万円
この調査は、日本歯科技工士会が3年ごとに定期的に行っている調査だ。
特徴は、歯科技工士会員が対象であるということだ。日本歯科技工士会の歯科技工士全体に占める会員比率は30%程度で、ベテランの技工士が多く、会費を支払っていることもあり「比較的豊かな技工士」と言われている。
歯科技工所アンケート
次に紹介するのは全国保険医団体連合会が行った「2016 年歯科技工所アンケート」というものから歯科技工士の年収を示したものだ。実際のデータは2016年歯科技工所アンケート調査結果と概要報告を参考にしていただきたい。
2016年歯科技工所アンケート
- 平均年齢:55.77歳
- 休日:週1 日が48.2%、ほとんど取れない30.5%
- 週労働時間:71~80 時間が16.3%、61~70 時間が14.5%
- 平均年収:317万円(300万円以下が53%)
このアンケートの特徴は、全国2,454件の歯科技工士(所)がアンケートに答えており、過去に類を見ない規模で実施されたのアンケートであることだ。
また、歯科技工士会の会員、会員以外関係なく行っている調査なので、最も業界の現状を反映していると言える。
また、このアンケートでは膨大な数の自由コメントを集め公開している。データだけでなく現役技工士の生の声が集められている貴重な調査結果だ。
歯科技工士の年収と実態のまとめ
まずは、歯科技工士の年収や労働実態の貴重な調査・アンケートを実施されいる日本歯科技工士会と全国保険医団体連合会に心より敬意を表したい。
双方の調査結果からは、過労死ラインを大幅に超える超長時間労働であるという実態が明らかになっている。そのことからも日本の歯科医療は歯科技工士の過重労働によって支えられていると言ってもよい。
そして、この調査結果は厚生労働省も日本歯科医師会も把握しているが、特に対策をとる姿勢は見られない。特に日本歯科医師会に至っては、闇献金問題や迂回献金問題と「政治と金」の問題を牽引している「自分たちさえ良ければよい」との考えの問題団体であることは明らかだ。
若い技工士が犠牲に
歯科技工士の年収や時給を実態に合わせて算出すると、歯科技工士の就労環境はとんでもなく劣悪な状況であることが分かった。
そして一番の被害者は若い技工士たちだ。「歯科医療を通じて社会に貢献したい」と夢と希望をもって歯科技工士という職業に就くこととなった彼らの約8割は5年以内に離職する。脅威の離職率8割をたたき出すブラック産業化を牽引しているのは誰なのか?
離職率8割の詳しい記事はこちら👉歯科技工士の実態と離職率!5年以内の離職率は?マジか80%
彼らは歯科医療にかかわる者たちの「見て見ぬふり」と「他人事」というような関わり方により未来を奪われている。
私が良い歯医者とは?と問われると、若い歯科技工士のような弱い立場のために勇気を持って行動する歯科医師と答える。そういう歯科医師は、困っている患者さんに対しても同じように接することが出来ると思う。
インテリ気取って辱めもなくしょーもない話をする歯医者ではなく、少数派であってもこのような歯科医師を応援したいし、そのような歯医者が患者さんから評価されるような情報を発信していきたいと考える。
お問合せ・コメントはこちら